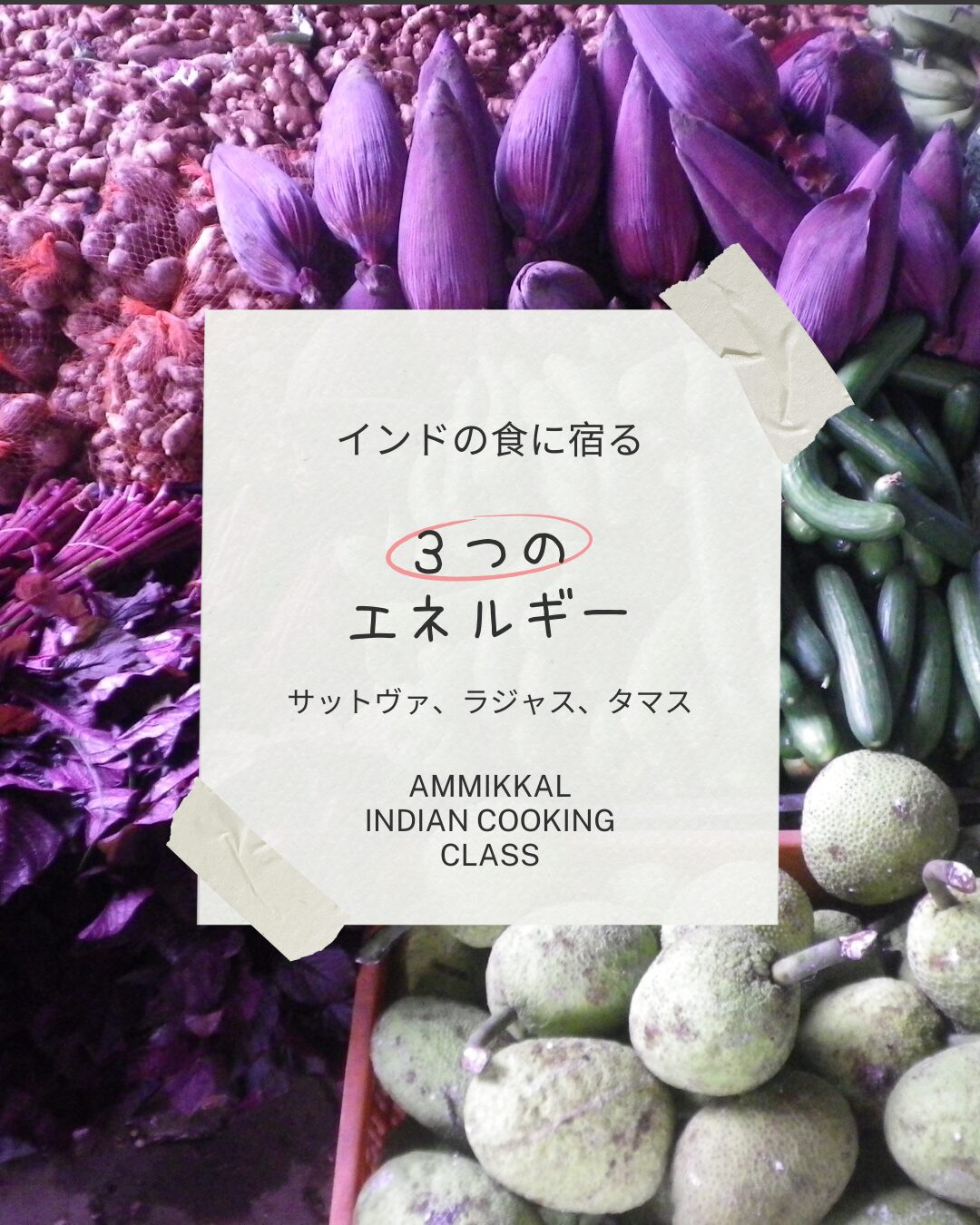南インドでは季節ごとに神聖な儀式や祭りが行われます。
先日行われた「ナヴァラトリ」は女神を讃えるお祭りで、人々は祈りと感謝を込めて、神様に“サットヴァ(純質)”に満ちた料理を捧げます。
今回は、インド哲学やアーユルヴェーダの基本概念「グナ(Guna)」の視点から、心と体を整える“サットヴァ”の考え方についてお話しします。
ナヴァラトリに込められた「サットヴァ」の祈り

南インドでは、ナヴァラトリの最終日になると、家庭で手作りの料理を神様にお供えします。
写真は、昨年の最終日に友人宅で供えられた、サットヴァにあふれる美しい食事。
すべてが植物性の「ピュア・ベジタリアン(純菜食)」で構成され、祈りのエネルギーに包まれています。
この「サットヴァ」という言葉には、インドの食文化や生き方の根幹が息づいています。
サットヴァとは? ― すべてを調和させる“純質”のエネルギー
料理教室やアーユルヴェーダのクラスでも、よく登場するキーワード「サットヴァ」。
インド哲学では、宇宙に存在するすべてのものが「3つのグナ(性質)」のバランスによって成り立っていると考えられています。
サットヴァ(Sattva:純質)
- 性質:軽快・調和・純粋・静けさ・知性
- 特徴:心が澄み渡り、穏やかで平和な状態。物事をありのままに見て、前向きな行動ができます。
ラジャス(Rajas:激質)
- 性質:動き・情熱・変化・活動・欲望
- 特徴:行動や創造の源になる一方、過剰になると怒りや焦り、ストレスを引き起こします。
タマス(Tamas:暗質)
- 性質:休息・停滞・重さ・無知・怠惰
- 特徴:睡眠や休息に必要な性質ですが、過剰になると無気力や停滞を感じやすくなります。
3つのグナのバランスが心と体を整える
これら3つの性質に「良い」「悪い」はありません。
私たちの心や身体の中には常に3つすべてが存在し、そのバランスが日々の状態を左右します。
ヨガや瞑想の実践は、サットヴァを高め、心を静めるための手段。
また、食事・行動・人間関係・環境の選び方によっても、サットヴァのエネルギーを育てることができます。
サットヴァな食事とは?
「どんな食べ物がサットヴァなの?」
「ラジャスやタマスを整えるには?」
答えは一言では語れません。
食べ物そのものの性質だけでなく、調理する人の心・食べる人の状態・環境すべてが影響するからです。
その深い世界は、料理教室やアーユルヴェーダクラスでじっくりお話ししています。
関心のある方は、ぜひ実際に体験してみてください。
おわりに ― “ピュア”の原点を見つめて
インドの食文化は、単なる菜食主義ではなく「生き方そのもの」に根ざしています。
次回は、南インドの「ピュア・ベジタリアン」文化についてもう少し掘り下げ、
どのように“ピュア”な心と食が結びついているのかをご紹介します。
ammikkal
インド食文化研究家/料理教室
インド各地で学んだ知恵と味を、日本の暮らしの中に伝えています。